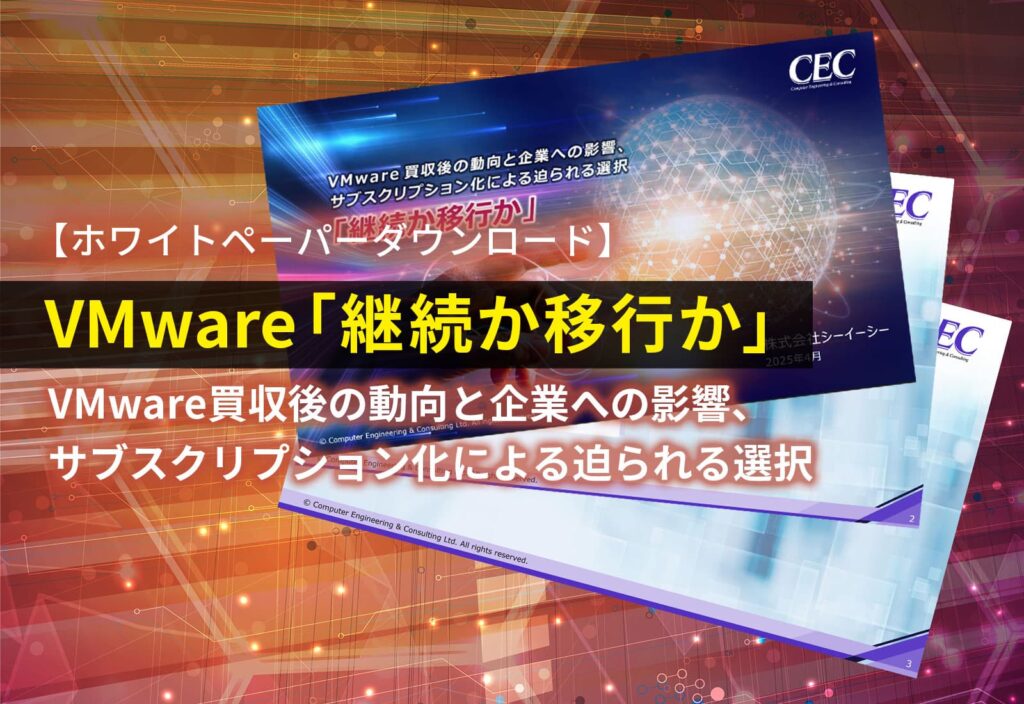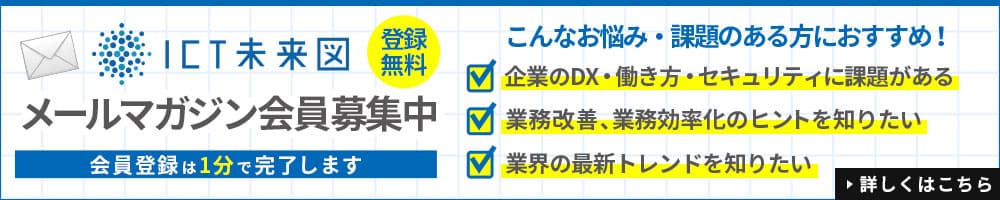オフコンとは? オープンシステムへの移行についても解説

オフコンとは?
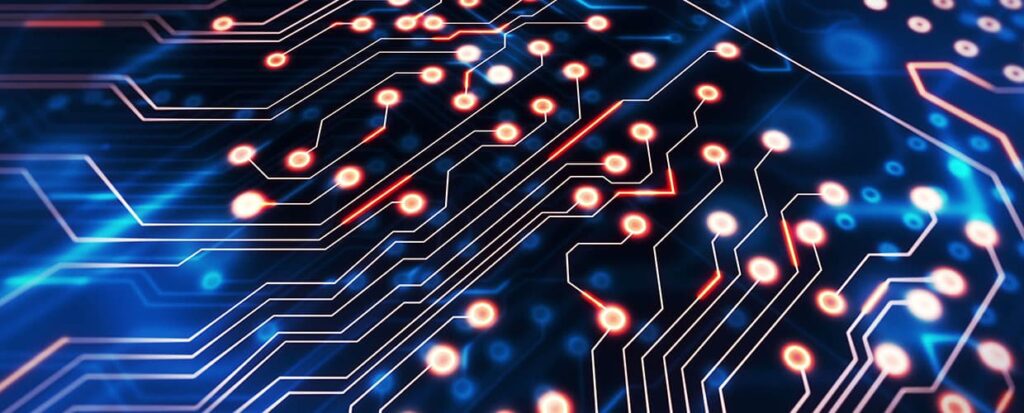
オフコンの概要
オフコンとは、オフィスコンピューターの略で、主に中小企業の事務処理を行うために設計された小型のコンピューターとして開発され、大企業向けの汎用機(メインフレーム)に対抗する形で普及しました。
メインフレームについてはこちらの記事から

このシステムは、財務会計や給与計算、販売管理などの業務に特化しており、日本国内では特に事務処理の効率化に貢献してきました。海外では「ミニコンピューター」や「ミッドレンジコンピューター」として知られるシステムですが、日本においてはオフコンという表現で広く親しまれてきました。
オフコンの誕生と進化の歴史
オフィスコンピューター(以下 オフコン)は、1960年代から1970年代にかけて日本で登場しました。1966年には東芝がTOSBAC-1100Dを発表し、1968年には三菱電機が「元帳会計計算機MELCOM81」を開発しました。このMELCOM81がオフコンの初号機とされています。その後も、富士通のFACOMシリーズやNECの日進月歩の技術革新により、オフコン市場は拡大しました。特に1970年代後半から1990年代にかけて、多くの中小企業で利用され、日本の商習慣や日本語処理に特化したその設計は、国内ビジネスに深く浸透しました。
しかし、1990年代半ばからのパーソナルコンピューター(以下 PC)の普及とコスト競争により、市場は徐々に縮小していきます。その結果、2010年代には多くのメーカーがオフコン製造から撤退する状況となりました。
オフコンが果たしてきた役割
オフコンは、企業ごとに業務に特化したシステムを提供し、事務処理の効率を大幅に改善する役割を果たしました。財務会計や給与計算といった事務処理に加え、在庫管理や販売データの集計といった商用計算を簡便に行える点が高く評価されていました。
さらにメーカーごとのカスタマイズ性や独自のプログラミング言語環境が、中小事業者特有のニーズに応える役割を果たしたのです。また、専用のハードウェアとソフトウェアが一体となったシステム設計は、使いやすさや信頼性の高さという大きなメリットをもたらしました。これにより、業務の効率化とともに経営資源の有効活用を可能にしてきたのです。
現在のオフコン市場の状況
現在、オフコン市場は縮小傾向にあり、レガシーシステムとして取り扱われています。1990年代の年間出荷台数は約3,000台でしたが、2020年には年間出荷台数が約160台程度にまで減少しました。
この背景には、クラウド技術やオープンシステムの普及といった要因が挙げられます。しかし、今もなお一部企業ではオフコンが運用されており、特に業務に最適化されたシステムを長年使用してきた企業が継続利用を選択するケースが見られます。一方、保守部品の確保やOSの対応・サービスの終了により、オフコンシステムの維持管理に課題を抱える企業が増えています。
オフコンの移行に関する動画はこちらから
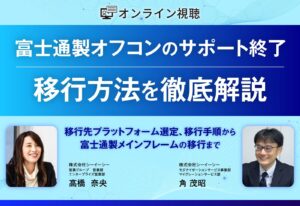
オフコンを利用し続ける問題点

主要メーカー撤退による保守部品やサポートの提供終了リスク
オフコンは、長年日本の中小企業や一部の大企業において業務を支えてきましたが、長期間利用し続けると、保守部品やサポートの提供終了といった問題に直面するリスクが高まります。現在では多くのメーカーが製造・販売を終了しており、直近では、エフサステクノロジーズ株式会社(※)が、Cloud Service for オフコンを2031年3月末に終了することを発表しました。既にNEC・日立・東芝といった主要メーカーも相次いでオフコン市場から撤退しており、今後、保守用部品の調達や修理サービスの提供が難しくなることが予想されます。この状況は、ハードウェアが故障した場合に業務が停止するリスクを高めており、信頼性の低下を避けるために対策が必要となります。
一方で、IBMは自社のオフコンシステム「IBMi」を引き続きサポートしていくことを明言しています。各社で方針が異なりますが、撤退するメーカーを使用している場合は、今後も製造・販売を継続する見込みのメーカーに移行するか、オープン化を行うか、2つの選択肢が考えられます。
- 2024年4月に富士通株式会社からサーバー・ストレージおよびネットワーク製品などを中心としたハードウェア事業を統合し、社名をエフサステクノロジーズ株式会社に変更されました。
継続利用か、オープンシステムへの移行か
各メーカーがオフコンに対して異なる対応を取る中、多くの企業がその利用を継続することと、オープンシステムへの移行を検討する選択肢の間で揺れ動いています。
現在も稼働する多くのオフコンは、老朽化したハードウェアやシステムの肥大化、改修や機能追加が困難なためトラブル対応の遅れといったリスクを抱えています。
撤退したメーカーのオフコンを継続して利用することによる最大のリスクは、デバイスやソフトウェアのサポート終了後に深刻な問題が発生した場合、業務が完全に停止してしまう可能性がある点です。特に、オフコンが企業の重要な業務システムを支えている場合、障害による影響は非常に大きくなります。また、メーカーのサポート終了後には障害発生時の復旧がさらに困難となり、最悪の場合には業務再開まで長期間を要する可能性もあります。結果として、企業全体の生産性や信頼性に悪影響を与える可能性が高まっています。これらは企業経営に直接的なダメージを与えるため、製造・販売を継続する見込みのメーカーに移行するか、オープンシステムへの移行を早急に計画しリスク管理を徹底する必要があります。
サポート終了システムに関してはこちらの記事でも触れています

データ活用の難しさ
オフコンは、設計当初から特定の業務に特化して作られてきたため、専用設計のOSやプラットフォーム上で動作しており、最新技術やシステム、クラウドサービスとの連携が極めて難しい特徴があります。これにより、蓄積された貴重なデータをクラウドサービスやAIといった現代の先端技術で活用することが、困難となっています。たとえば、クラウドを利用したセキュリティの強化やデータバックアップの容易化、AIを用いたデータ分析による業務最適化といった施策を実現するには、オフコンの現状を大幅に見直し、移行を進める必要があります。
オフコンから新たなシステムへデータ移行をする際に、複雑かつ費用がかかることもデータ活用を阻む一因となっており、業務の競争力向上を目指す企業にとって、既存の制約を打破することが急務となっています。
運用管理の高騰
オフコンの専用ハードウェアやソフトウェアの維持などの運用コストは年々増加し、企業にとって負担となっています。古いシステムを維持するためには、オフコンに精通した技術者が必要であり、人件費や保守費用の高騰が背景にあります。また、技術者不足により、専門知識を持つサポート要員が減少していることも課題です。
このような状況下では、システム障害が発生した場合に即座の対応が期待できず、業務に大きな影響を与える可能性があります。メーカーのサポートが終了している場合、独自に外部の技術者を雇用する必要があり、これも運用負担を増大させる要因となります。
また、電力消費やサーバールームの維持管理といったランニングコストも、現代の省エネルギー型のシステムに比べて割高になる場合もあるでしょう。さらに、新しい技術や市場競争の影響を受けにくい専用設計であることが、運用管理費用の高騰につながっています。
オフコンからオープンシステムへ。特徴と移行メリット

オープンシステムとは?
オープンシステムとは、特定のメーカーやベンダーに依存せず、多様な環境での相互運用性を実現し、広く普及している標準的な技術や規格に基づいて設計されたシステムのことを指します。これは従来のオフコンのようなメーカーが独自に設計したシステムと異なり、さまざまなハードウェアやソフトウェアと互換性を持つため、ユーザーが柔軟に選択して導入することができます。
オープンシステムは特定の技術やサービスへのロックインが少ないため、拡張性や移行の自由度が高く、新しい技術やサービスに迅速に対応できる柔軟性を備えています。
オープンシステムの柔軟性
オープンシステムは、異なる環境やプラットフォームへの対応が容易であるため、非常に柔軟性が高いシステムといえます。従来のオフコンが特定のメーカーや仕様に制約されていたのに対し、オープンシステムでは広範なソフトウェアやハードウェアオプションから最適なものを選択できます。つまり、多様な業務ニーズに応じてシステムの一部をカスタマイズしたり、新しいアプリケーションやサービスを導入したりする際に、大幅な手直しを抑制します。これにより、企業は業務要件や予算に応じてシステムをカスタマイズでき、効率的な運用が可能です。オフコンのような専用設計だと適応が難しい部分を、オープンシステムではスムーズに実現できるため、変化の激しいビジネス環境において大いに役立つといえるでしょう。
外部サポートが受けやすい環境の構築
オフコンのような専用システムの場合、特定のベンダーだけがサポートを提供することが多く、選択肢が限られていました。また、メーカーのサポートが終了すると運用が困難になります。しかし、オープンシステムは、標準的な技術や規格に基づいて構築されているため、トラブルが発生した場合でも外部の専門家から迅速かつ適切なサポートを受けることが可能です。また、複数のベンダーやサービスプロバイダーで競争があるため、費用対効果の高いサポートを選ぶことができます。
コスト削減効果と運用効率化
オープンシステムへの移行は、長期的に見て大きなコスト削減効果をもたらします。専用ハードウェアやソフトウェアに縛られないため、初期導入コストや運用管理コストを削減できます。さらに、運用プロセスの効率化が図れるため、IT部門の負担軽減や、より戦略的な業務へのリソース配分が可能となります。
システム運用におけるコスト削減は、多くの企業にとって重要な課題です。オフコンなどの専用システムでは、ハードウェアや保守サービスが高額であるうえ、ベンダーが限定されているため競争原理が働きにくく、コストが増大しやすい構造があります。一方、オープンシステムでは、標準化された部品やソリューションが豊富に存在し、選択肢が広がることで価格競争が起きやすく、コストの抑制が可能です。また、運用効率化の面でも、クラウド型ソリューションや統合管理ツールとの連携が容易なため、人的リソースの削減が期待できます。
クラウドやモダン技術との親和性
オープンシステムは、クラウド環境やモダンな技術との高い親和性を持っています。特にクラウド移行を考える企業にとって、オープンシステムは理想的な選択肢です。クラウドサービスを利用することで、従来のオフコンのように物理的なサーバーや設備に依存することなく、柔軟でスケーラブルなシステム運用が可能となります。また、クラウドプラットフォームとの連携を活用することで、スケーラビリティや可用性の向上が実現します。さらに、リホスト技術やコンテナ化といったデジタル変革を支える最新技術への適応も優れており、AIやビッグデータ解析といった最新技術をシステムに取り入れやすくなり、企業の競争力強化にもつながります。
オープンシステム向けソリューション NetCOBOLへの移行
オフコンを利用し続ける代わりにオープンシステム向けソリューションへの移行する一つの例として、さまざまな企業がNetCOBOLへの移行を進めています。NetCOBOLは、富士通製のオフコンマイグレーションサービスにおいて使用されるCOBOLの一種で、オフコンで多用されてきたCOBOL言語の資産を活かしつつ、オープン系の汎用プラットフォーム上でそれを動作させることを可能にします。このアプローチにより、オフコン特有の高コスト構造や人材不足という問題を緩和することができるほか、クラウドサービスやモダン技術との親和性も大きなメリットとなります。製造業やサービス業をはじめとする多くの企業が、移行コスト以上の長期的な運用コスト削減効果を享受できる点も、NetCOBOLの注目が高まる理由でしょう。
オフコンから移行する際の課題と対策

データ移行プロセスの難しさ
オフコンからオープンシステムへの移行で最も大きな課題の一つが、データ移行のプロセスの難しさです。オフコンは、メーカーごとに独自の設計がされており、データ形式やデータベース構造の標準化がされていない場合も多くあります。データを新しいシステムに移行する際、フォーマットの変換、整合性の確保、データ量の管理に多大な手間がかかることが少なくありません。特に、長年運用してきたオフコンシステムでは膨大な量のデータが蓄積されており、重複や欠損が含まれている可能性もあり、品質を確保するための追加作業も必要です。この課題に対応するために、専門的なデータ移行ツールの利用や経験豊富な技術者との連携が不可欠です。データ移行がうまくいかない場合、業務の継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、移行を進める際には、正確で計画的なアプローチを取ることが重要です。
現行システムに合わせた環境設計
オフコンからの移行においては、現行業務の運用方法に応じて新しいオープンシステムを最適化する環境設計が求められます。オフコンは特定の業務に特化したシステム構成である場合が多く、単純なハードウェアやソフトウェアの変更ではカバーできない部分が出てきます。そのため、現状の業務を分析し、新しいシステムへ移行する際に影響を最小限に抑えるための環境設計が鍵となります。オフコン独自の業務フローに依存している場合、新システムへの適応を図るには現行業務を分析し、それに合わせたカスタマイズまたは再設計を行う必要があります。しかし、業務の効率化や柔軟性を目的とした「単純に同じものを新しい環境に持ち込む」だけではなく、業務を見直す絶好の機会と捉えることが重要です。移行計画を進める際には、内製化の能力と外部サポートのバランスを考慮しながら設計することで、スムーズな移行が可能になります。
移行中のダウンタイム
オフコンからオープンシステムへの移行では、システムを一時的に停止しなければならないダウンタイムが避けられない場合があります。このダウンタイムが業務に与える影響は、企業の規模や業種によって異なりますが、長時間に及ぶ場合、顧客対応や事業活動に支障をきたすリスクが高まります。そのため、移行計画を立てる段階で、移行作業を複数の段階に分割する、あるいは休日や業務の閑散期を利用して作業を行うなど、ダウンタイムを最小化する工夫が必要です。また、移行後に直ちに業務が再開できるよう、包括的なテスト環境を構築し、事前に徹底的な動作検証を行うことが推奨されます。
移行コストの管理
オフコンの移行プロジェクトには、初期投資コストや人件費、ツール使用料など、さまざまなコストが発生します。特に、オフコン特有のシステムやデータ形式に対応するためにカスタマイズが必要な場合、費用が予想以上に膨らむことがあります。このため、移行の計画段階から予算を明確にし、発生し得るコストを細かく見積もることが重要です。パッケージ製品やクラウドの導入、データ移行や環境設計にかかるコストが、企業の予算に大きく影響する可能性があります。また、クラウド対応や外部ベンダーの支援を活用することで、初期費用を抑える選択肢も検討すべきです。移行後の運用コストやメンテナンス費用も想定し、総コストを見据えた上で最もコストパフォーマンスの高い方法を選択することが、成功の鍵といえます。
オフコンのオープンシステム移行ならRe@noveにお任せください

シーイーシーのマイグレーションサービス「Re@nove」では、富士通製オフコンのマイグレーションに特化したソリューションを提供しています。リホストやクラウド・オンプレミス移行など、企業のニーズに応じた最適な移行手法を提案し、移行プロセスをワンストップで全面的にサポートできるサービスです。
高い技術力と豊富な経験に基づき、効率的な移行計画の策定を支援します。移行後の運用支援も充実しており、安心して新しいIT環境を整えることが可能です。
富士通製オフコンマイグレーションサービスには、次のような特長があります。
- 短期間、かつ低リスクでマイグレーションできるリホスト形式を採用
- クラウド・プライベートクラウド・オンプレミスなど最適な移行先を選定
- マルチベンダー、マルチプラットフォームへの移行も柔軟に対応

まとめ
オフコンの役割や歴史、そして現代における移行の重要性について解説しました。オフコンは日本の中小企業における事務処理を支える重要な存在として、その時代ごとのビジネスニーズに応じた進化を遂げてきました。しかし、現在では市場が縮小し、保守部品や専門技術者の不足など、利用を続ける上でのリスクが顕著になっています。そのため、多くの企業がオフコンマイグレーションを検討し、オープンシステムへの移行を実施する動きが見られます。この移行により、コスト削減や運用の効率化、さらにはクラウド環境や最新技術との親和性の向上といった多くのメリットが得られるでしょう。
一方で、データ移行の難しさや移行コストの管理といった課題も存在します。しかし、これらの課題を適切に計画的に対処することで、企業は競争力を維持し、将来的な成長基盤を確立することが可能です。富士通製オフコンなど主要メーカーの撤退や、市場での役割が変化する中、オフコンの役割と歴史を学びつつ、現代のニーズに合ったシステム導入を進めていくことが必要となっています。
オフコンの移行に関する動画はこちらから
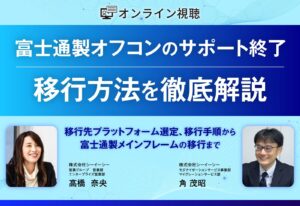
今後、企業が生き残るためには、オフコンをそのまま利用し続ける選択肢よりも、オープンシステムへの移行を見据えた対応が求められています。現状の課題を克服し、効率的な業務環境を目指すためにも、適切なシステム選択と計画が求められることは明らかです。柔軟で効率的なシステム構築を目指し、課題を一つずつ解決しながら、次世代のIT基盤へつなげていくことが重要です。オープンシステムへの移行を通じて、企業の持続可能な成長を実現していきましょう。
マイグレーション関連の資料はこちらから
-

【ホワイトペーパーダウンロード】VMware「継続か移行か」- VMware買収後の動向と企業への影響、サブスクリプション化による迫られる選択
-


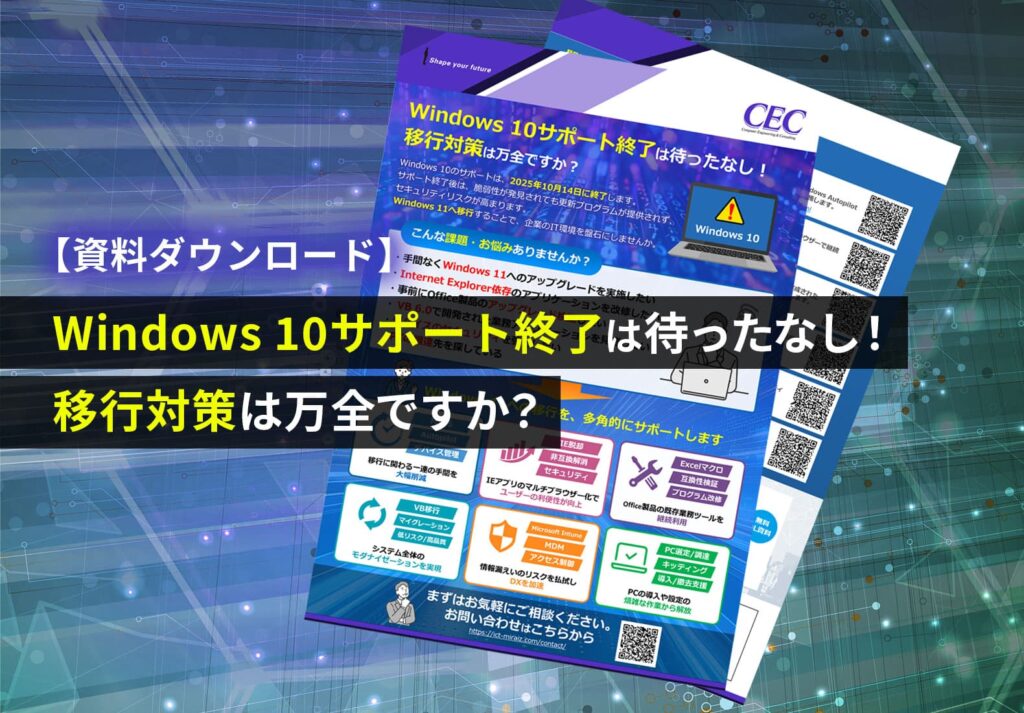
【資料ダウンロード】Windows 10サポート終了は待ったなし!移行対策は万全ですか?
-


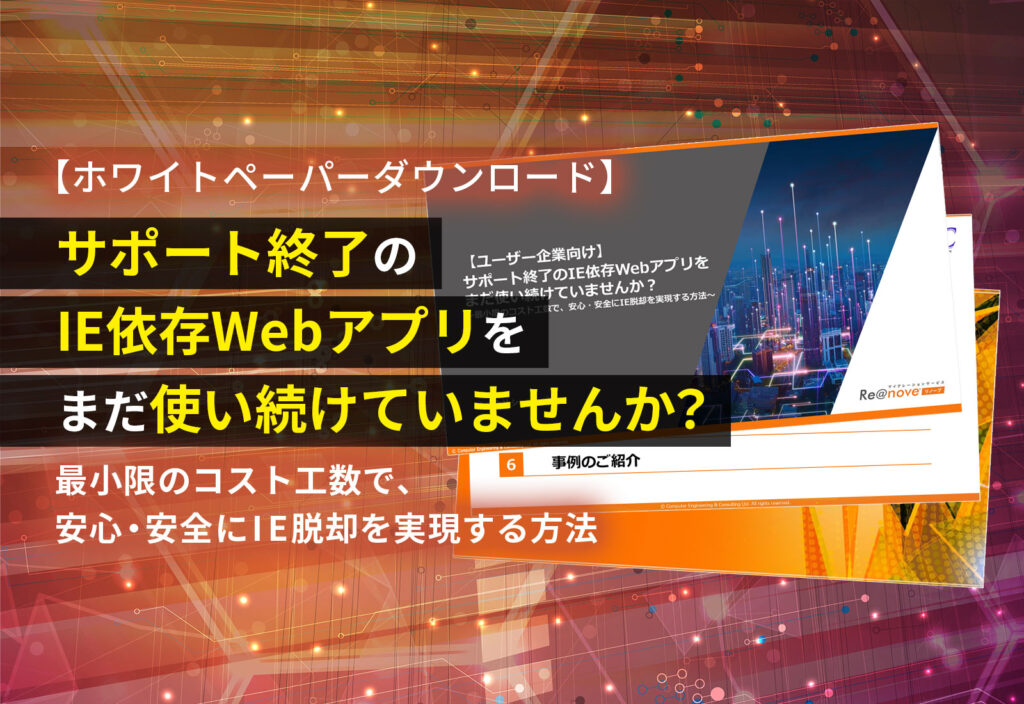
【ホワイトペーパーダウンロード】サポート終了のIE依存Webアプリをまだ使い続けていませんか? ~最小限のコスト工数で、安心・安全にIE脱却を実現する方法~
-


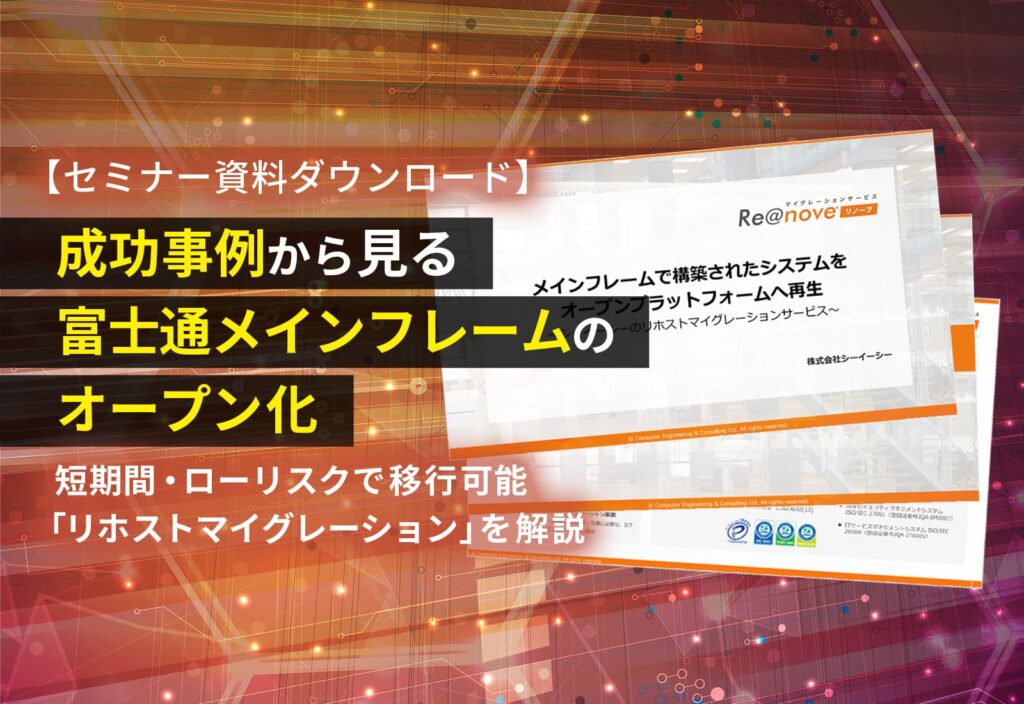
【セミナー資料ダウンロード】成功事例から見る、富士通メインフレームのオープン化 〜短期間・ローリスクで移行可能「リホストマイグレーション」を解説〜
-



【ホワイトペーパーダウンロード】メインフレームで構築されたシステムをオープンプラットフォームへ再生
-


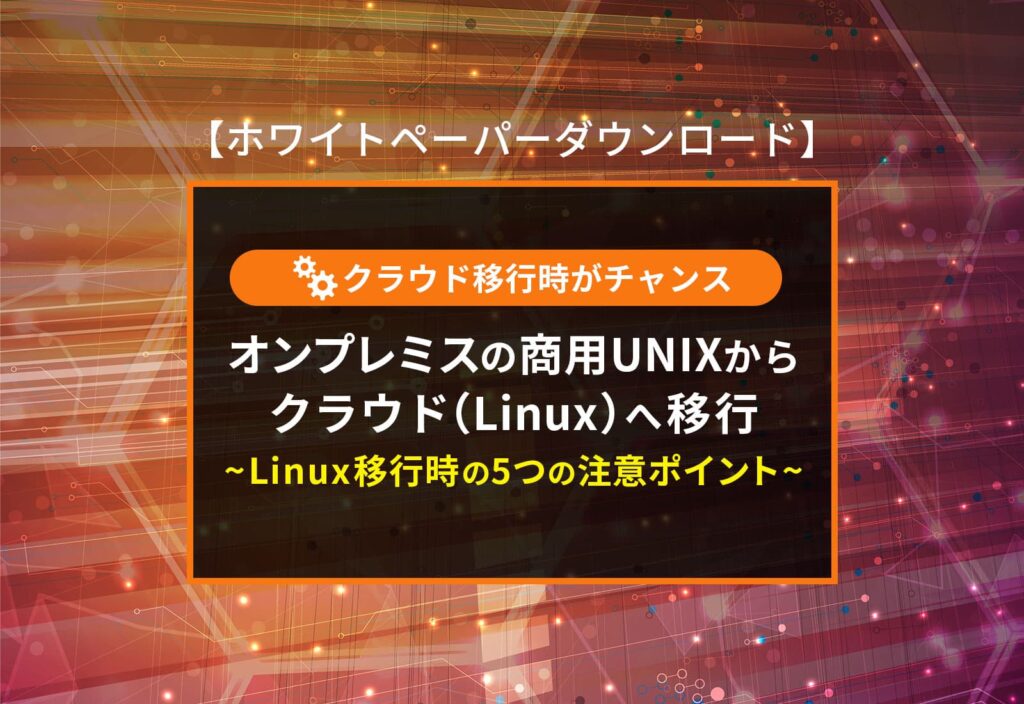
【ホワイトペーパーダウンロード】オンプレミスの商用UNIX(Solaris、AIX、HP-UX)からクラウド(Linux)へ移行 ~Linux移行時の5つの注意ポイント ~
-


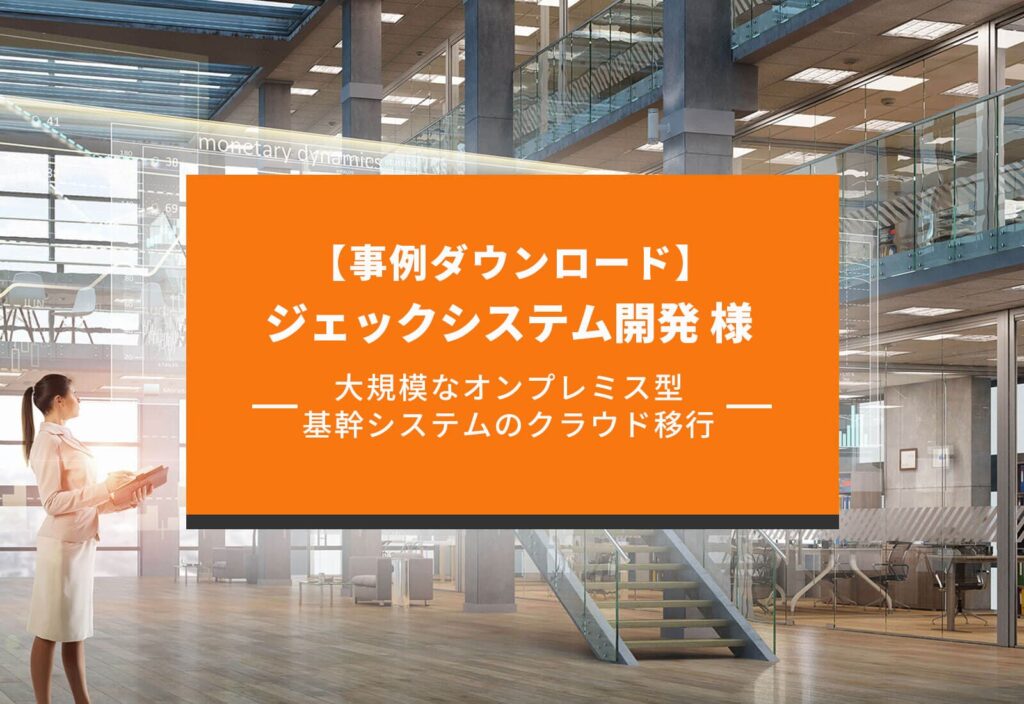
【事例ダウンロード】ジェックシステム開発様-大規模なオンプレミス型基幹システムのクラウド移行-
-



【ホワイトペーパーダウンロード】継続利用は危険!Visual Basic 6.0からのマイグレーションを低リスク&高品質で実現!
-



【事例ダウンロード】ラジオメーター株式会社 様 VB.NETへの移行 システムの従来機能を100%再現
マイグレーション関連の動画はこちら
-



【オンライン視聴】仮想化基盤を取り巻く市場の変化、今、Red Hatで実現する柔軟な仮想化基盤
-


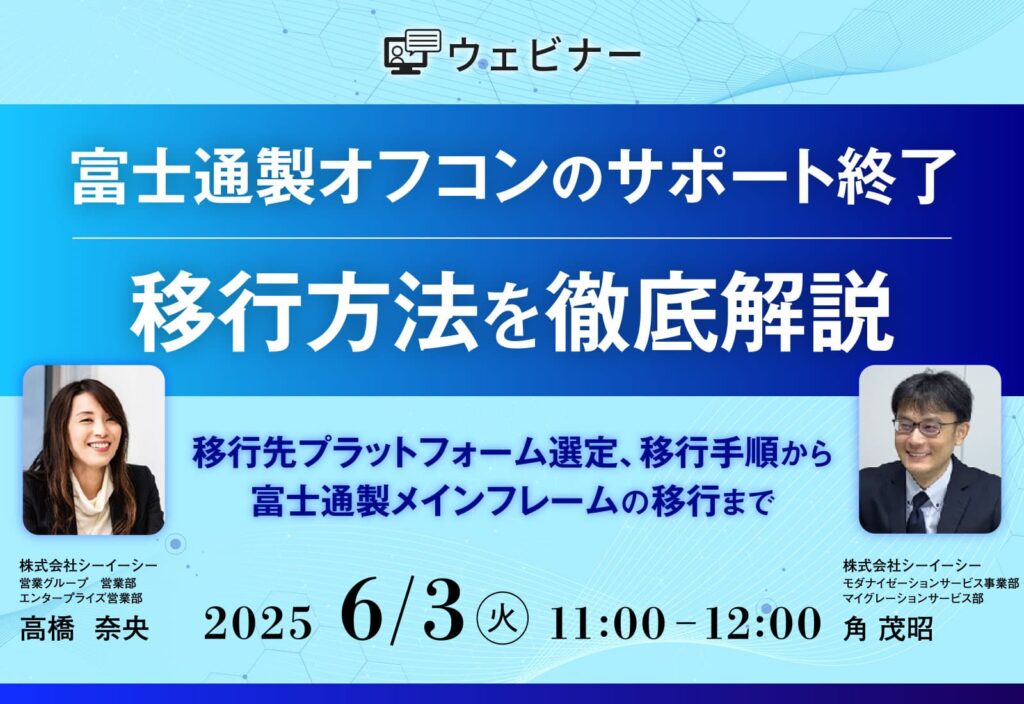
【オンライン視聴】富士通製オフコンのサポート終了、移行方法を徹底解説~移行先プラットフォーム選定、移行手順から、富士通製メインフレームの移行まで~
-



【オンライン視聴】オープン化やクラウド移行で解決!マイグレーション成功のカギ〜シーイーシーのリホストマイグレーションサービス~
-


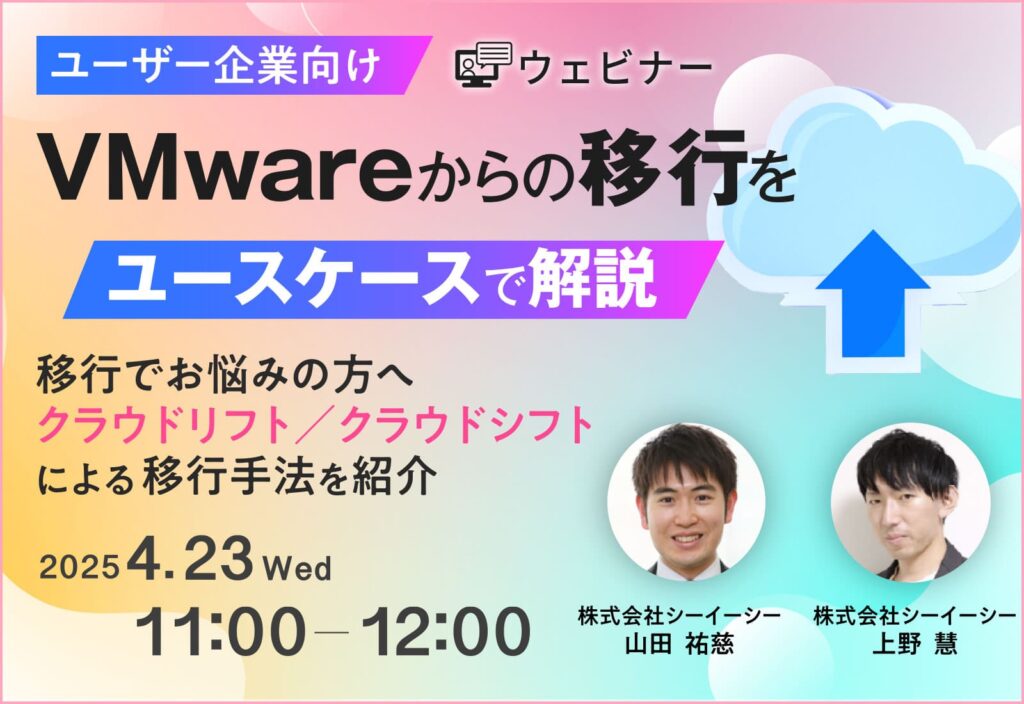
【オンライン視聴】【ユーザー企業向け】VMwareからの移行をユースケースで解説 ~ 移行でお悩みの方へ、クラウドリフト/クラウドシフトによる移行手法を紹介 ~
-


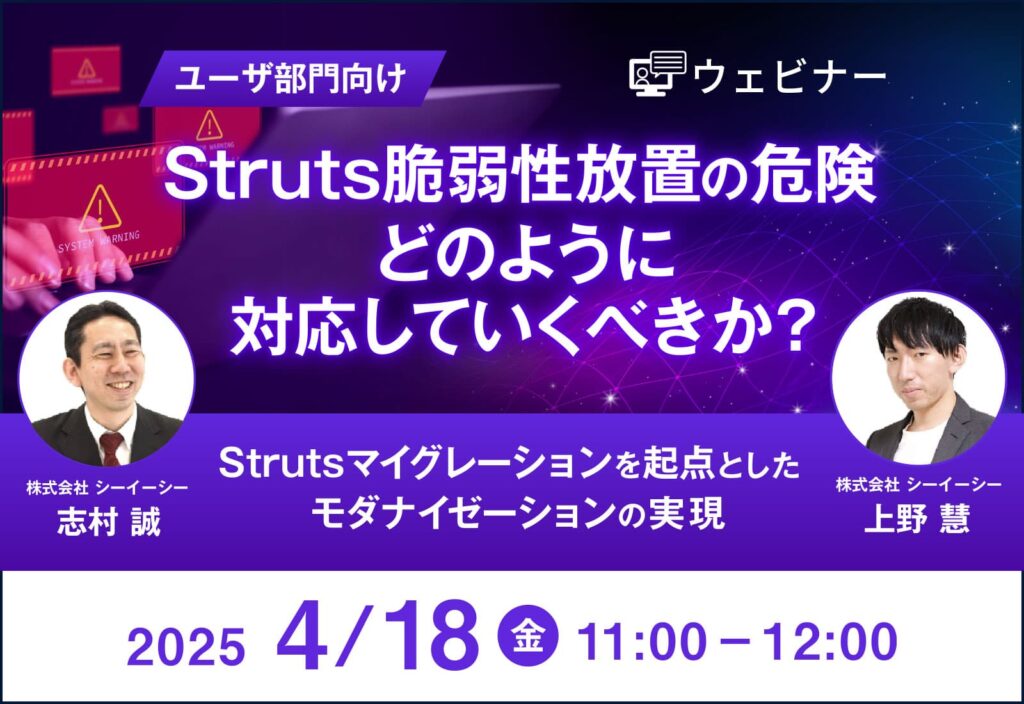
【オンライン視聴】【ユーザ部門向け】Struts脆弱性放置の危険 、どのように対応していくべきか? ~Strutsマイグレーションを起点とした、モダナイゼーションの実現~
-


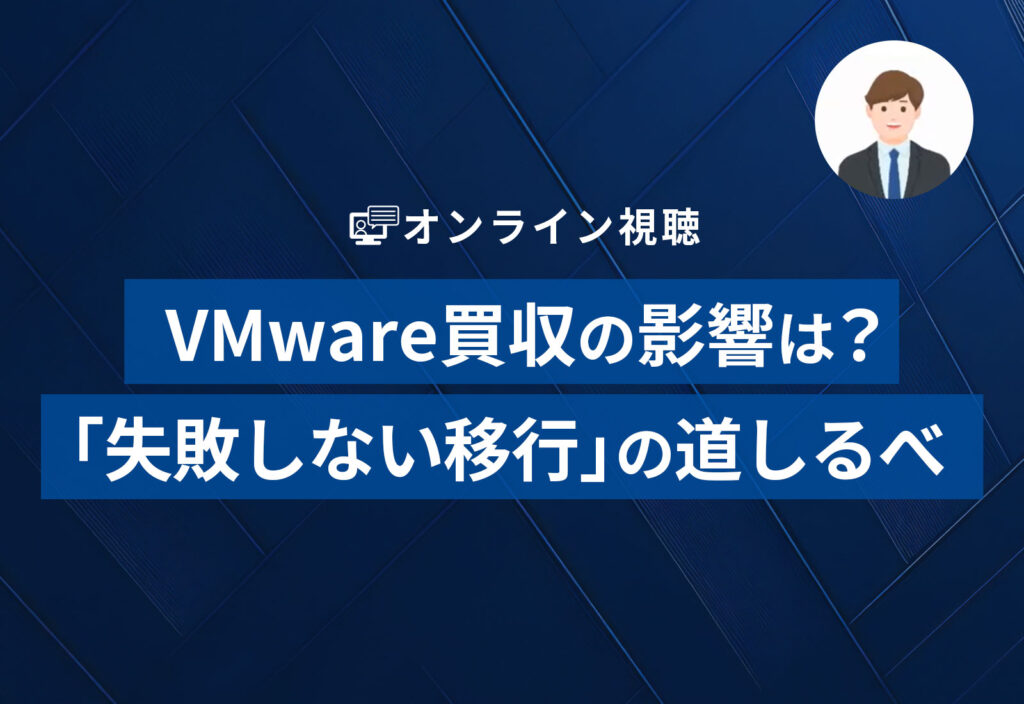
【オンライン視聴】VMware買収の影響は?「失敗しない移行」の道しるべ
-


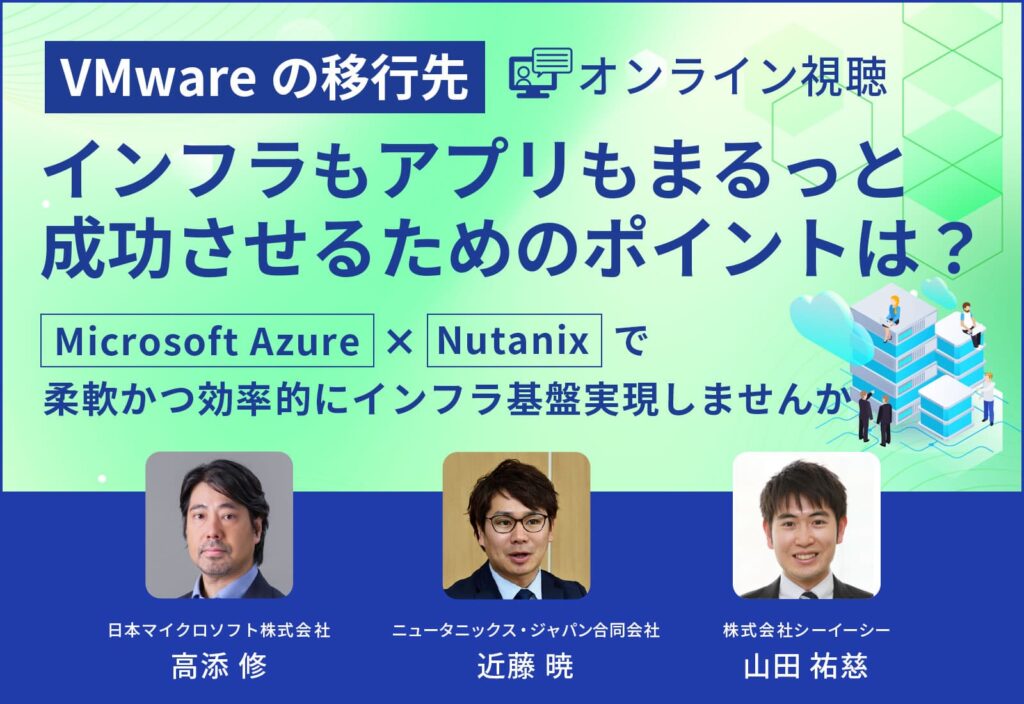
【オンライン視聴】VMwareの移行先、インフラもアプリもまるっと成功させるためのポイントは?~Microsoft Azure × Nutanixで柔軟かつ効率的にインフラ基盤実現しませんか~
-



【オンライン視聴】VMwareの移行先、どう選ぶ?〜Red Hat OpenShiftで実現する、安全・安心なVMware移行〜
-


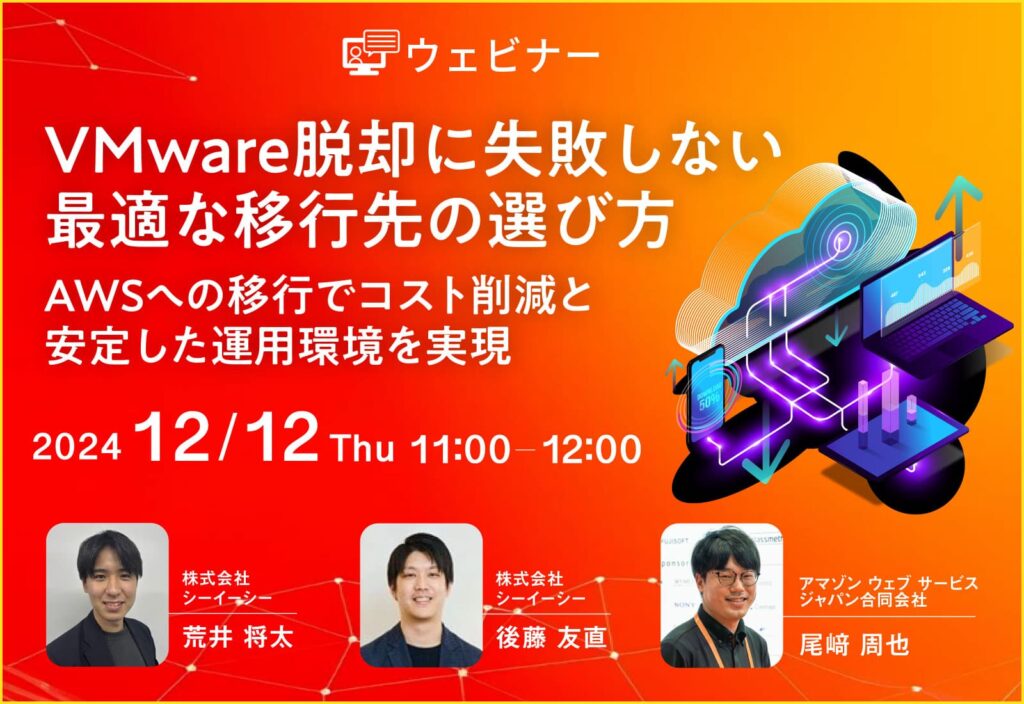
【オンライン視聴】VMware脱却に失敗しない、最適な移行先の選び方 〜AWSへの移行でコスト削減と安定した運用環境を実現〜
関連サービス


オフコン(オフィスコンピューター)で構築されたシステムをオープンプラットフォームへ再生
「富士通製オフコンマイグレーションサービス」