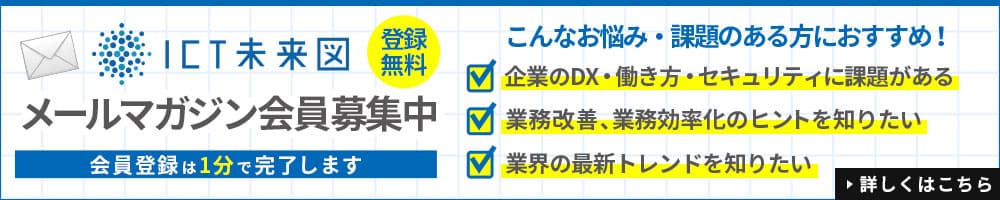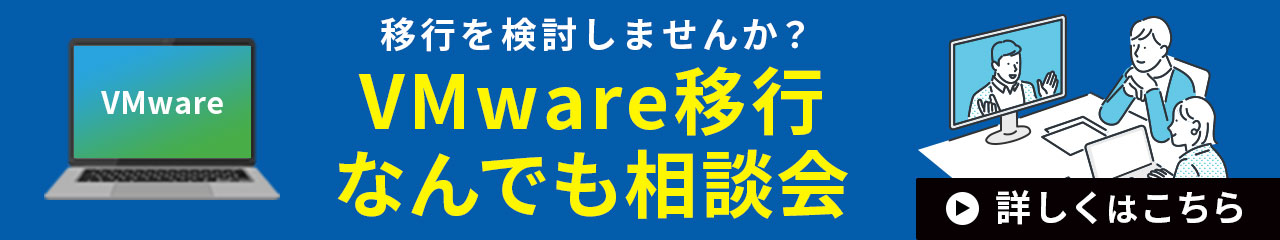VMware社 買収後の動向、迫られる選択肢と最適な移行先とは

企業の仮想環境を支えてきたVMware社は、Broadcom社に買収されたことで、今後の展開が不透明になっています。業界をリードする仮想化技術を使った、極めて依存度の高いサービスであったため、VMware製品(以下 VMware)を導入している企業はその後の対応に追われています。
 未来図編集部
未来図編集部VMware社の買収によって仮想環境はどのように変化し、ユーザーにはどのような選択肢があるのでしょうか。
また、既存環境の維持は企業にどのようなリスクをもたらす可能性があるのでしょうか。
この記事ではVMwareを取り巻く環境の動向や、ユーザーに求められる対応について整理いたしましたので、今後の計画を立てる際にぜひ参考にしてください。
Broadcom社が描くVMwareの未来とユーザーへの対応


VMware社をおよそ610億ドルで買収したBroadcom社は、VMware社が培ってきた仮想化技術のノウハウとリソースを傘下に置くことに成功しました。



ソフトウェア事業の拡大に向け、同社はVMware社を取り巻く環境の大幅な刷新に動いています。
2023年のBroadcom社によるVMware社の買収後、大きな変化が生じたのがライセンス形態の変更です。VMwareは今後サブスクリプションモデルに限定したサービスの提供を予定しているため、多くの企業が対応に追われています。
サブスクリプションモデルは、近年ほとんどのSaaS製品が採用している料金形態であり、同社もその流れに沿ったものと思われます。ただし、この料金形態の変更は、多くの企業にとってコストの上昇やサービスプランに関する柔軟性の低下といった課題をもたらすことから、混乱を招いているのが現状です。
VMware社の買収と企業への影響についてはこちらの記事でも紹介しています。


販売終了に伴う永久ライセンスのサポート方針を発表



Broadcom社は、2023年12月にVMwareの永久ライセンスの販売を終了する決定を発表しました。
これはサブスクリプション形態への完全移行のファーストステップとなりますが、同時に既存ユーザーを支援するための施策は継続して提供するとしています。
発表によると、既存のVMwareの永久ライセンスは引き続き使用可能であり、ゼロデイセキュリティパッチも無償で提供されるとのことです。また、サブスクリプションへの切り替えを希望するユーザーには、移行期間中に延長サポートが提供されます。
ただし、これらの措置は暫定的なものであるとも考えられます。永久ライセンスの販売が停止したことを踏まえると、既存の永久ライセンスユーザーに対して現在と同じサポートが提供され続けるかどうかは、保障されていません。
EUC事業売却と新会社Omnissaの始動


Broadcom社は、VMware社のEUC事業を2024年2月に売却すると発表しました。EUC事業には主力製品の一つでもあったVDI製品も含まれており、同事業は独立した形で新会社「Omnissa」として設立されました。
Broadcom社が直接VDIを扱うことはなくなり、代わりにOmnissaが仮想デスクトップ製品の「Horizon」と、統合エンドポイント管理製品「Workspace ONE」の提供を継続するとのことです。
Omnissaは、既存のソリューションの強化による、デジタルワークスペースの効率化と安全性の向上を目指しています。これは、仮想デスクトップ環境を最適化することで、エンドユーザーに快適な作業環境を提供することを意味しています。
VMware Explore 2024で発表された今後の展開
VMware Explore 2024では、Broadcom社が描く新しいビジョンが発表されました。同社のリニューアル製品である「VMware Cloud Foundation 9」は、構築プロセスの簡略化とコスト削減を実現し、企業がクラウド環境をより効率的に運用できるように設計されています。
同時に発表された「VMware Private AI」では、AI活用に必要なハードウェアサポートの拡充と、vGPU管理機能の向上が発表され、AI導入を加速させる基盤活用が促されています。
エンタープライズ分野における課題解決を新しいアプローチで目指すものであることから、多くのエンジニアが関心を寄せています。
VMware Explore 2024の詳細はこちら


デスクトップ仮想化製品を完全無償化
Broadcom社は、生まれ変わったサービスをより広く普及すべく、仮想デスクトップ製品「VMware Workstation Pro」と「VMware Fusion Pro」を個人利用に限り無償化する方針を発表しました。個人ユーザーが高度な仮想化ツールを無料で利用できることで、技術スキルの向上や開発環境の試験導入が促進されることが期待されます。



一方で、商用利用の場合は基本的には引き続きライセンス契約が必要であり、無償化の対象外となる点は注意しなければなりません。
混迷する市場と関連会社の動き


VMwareの抜本的なライセンス体系の変更は、関連企業や市場全体に大きな影響を与えています。OEM契約の見直しや、新しい販売モデルの導入によって、従来のパートナーシップが再構築されつつあるのが現状です。特に日本国内の市場では、販売体制の変化が目立ち、多くのエンジニアや企業が新しい状況に対応する動きも見られます。
OEMパートナーの見直し
OEM契約の見直しにより、日本国内のサーバーメーカーによるVMwareを含んだ、パッケージ製品の販売を終了する動きが相次いでいます。



新規販売に加え、既存製品の保守サービスに関しても、見直しや提供自体が難しい状況に陥っており、トラブルの発生が懸念される状況です。
これまで、日本ではOEMパートナーシップを経由して展開されてきたVMwareですが、Broadcom社の買収後、新しいビジネスモデルへの移行が余儀なくされています。VMware導入企業に加え、国産メーカーを含むパートナー各社の事業戦略に影響を及ぼしているため、抜本的な見直しを求められている会社も少なくないでしょう。
AWSによるOEM販売の中止
AWSは「VMware Cloud on AWS」に関するOEM契約の終了を発表しました。今後の更新や拡張については、Broadcom社や認定リセラーを通じて行うとしています。
この動きは、AWS自身の販売戦略の再構築が求められていることを示唆するニュースです。エンドユーザーにとっては、契約更新や製品拡張における選択肢が変わるため、適切なサポートを得るための情報収集が必要になっているともいえるでしょう。企業のクラウド戦略においても、この変更がどのような影響を与えるか注目されています。
新たなOEM契約「Value-Add OEM(VAO)」を締結
もう一つ注目したいのが、Vmwareによる新たなOEM契約モデル「Value-Add OEM(VAO)」の導入です。日本市場での提供体制を再構築したこのモデルを用いて、日立やエフサステクノロジーズが相次いで販売を再開し、国内市場での製品提供が再び強化されています。



ただし、ビジネスモデルの抜本的な刷新だけでなく、円滑にモデルシフトを遂行するための取り組みも、進められつつあります。
一連の動向に対するユーザーへの影響


Broadcom社によるVMware社の買収、およびライセンスモデルの変更は、多くの企業にとって重要な転機となる出来事となりました。これらの動向は、特にコストやサポート体制の面でユーザーに大きな影響を与えており、慎重な対応が求められています。
中でもサブスクリプションモデルへの移行が半ば強制されていることは、コスト上昇や運用の負担増加をもたらすとされ、大いに懸念されているのが現状です。
懸念される継続利用のコスト高
Broadcom社によるライセンス体系の変更は、多くの企業にとってコスト管理の再検討を迫る要因となりました。サブスクリプションモデルは、周到な運用計画をあらかじめ立てておかなければ、キャッシュフロー悪化の要因となるためです。
もちろん、一部の企業にとってコスト削減の恩恵をもたらす可能性がありますが、コストの上昇に対応できない企業も出始めるでしょう。



特に、小規模な運用環境を持つ企業にとっては、この変化が大きな負担となり得ます。
エンジニアや運用担当者はこうした状況を見越し、より効率的な運用計画を策定しなければなりません。
サポート終了により迫られる対処
Broadcom社は、既存の永久ライセンスユーザーに対して移行期間を設けていますが、すべてのユーザーが提示されたスケジュール通りに移行できるとは限りません。この移行プロセスには、既存のインフラを調整するための時間やリソースが必要であり、多くの企業が課題を抱えています。
特に、サポート終了に伴う移行の準備不足は、重大な障害となり得るかもしれません。技術的な対応や運用計画の遅れにより、事業に悪影響をもたらすリスクがあります。
こうした状況では、ユーザー企業が移行計画を早期に策定し、サービスを継続して使い続けるのか、あるいは新しいサービスの利用をスタートさせるのか、検討が求められています。
ユーザーがとれる選択肢


VMwareのライセンス形態の変更により、遅かれ早かれユーザーは新しい環境への適応を進める必要があります。
ユーザーが選べる選択肢としては、現状維持、VMwareサブスクリプションへの移行、または他サービスへの移行という三つの選択肢です。
現状維持の場合は、永久ライセンスのサポート期間内に検討が必要



永久ライセンスを現状維持する選択肢では、サポート期間が終了するまでの間に将来的な運用計画を立てる必要があります。
現状維持は残念ながら将来性のある選択肢とはいえず、これ以外の措置をいずれは選択しなければなりません。また、移行計画の未整備や対応の遅れは、サポート終了後に運用面において重大な影響を及ぼす可能性もあります。
VMwareサブスクリプションへの移行


VMwareサブスクリプションへの移行は、Broadcom社が強く推奨する選択肢です。永久ライセンスからサブスクリプションライセンスへの移行により、製品の最新バージョンや追加機能が利用可能となり、長期的なサポートを受けられます。
ただし、同ライセンスへの移行には、これまで紹介してきた通り、コスト面での課題が挙げられます。適切な運用計画を策定できない場合、さらなる負担が生じる可能性も懸念されます。
他サービスへの移行



今回のライセンス形態の変更に伴い、VMwareから他サービスへの移行を検討する企業も増えています。
仮想環境市場では、そのほかの競争力のある代替サービスが充実しており、必ずしもVMwareに固執する必要はありません。
他サービスへの移行では、現在利用中のアプリケーションやシステムとの互換性および、運用コストが重要な検討事項となります。また、移行に伴う初期コストを抑えるため、各サービスが提供するプロモーションや移行支援プログラムを活用することも検討しましょう。
最適な移行先とは
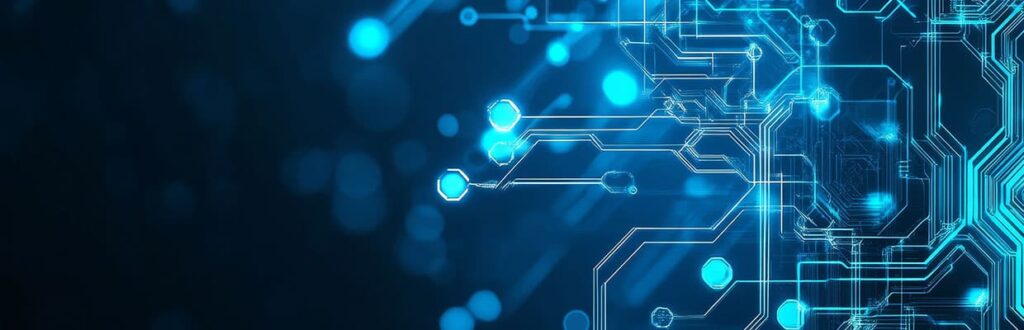
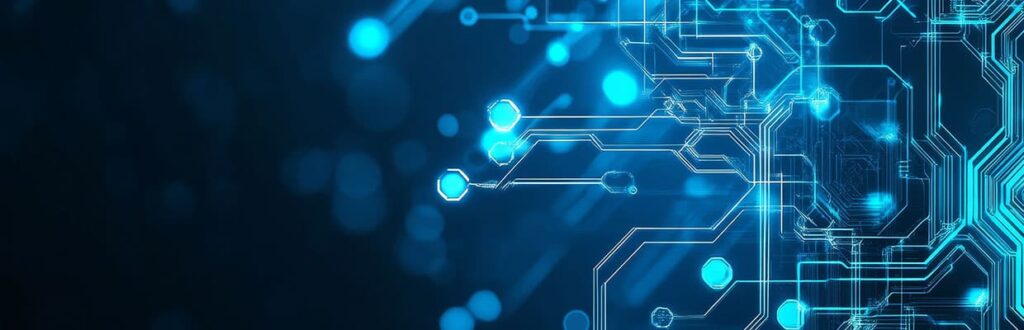



移行先はクラウドに限定せず、オンプレミス(データセンター)を含む幅広い選択肢から検討することもおすすめです。
クラウド移行には柔軟性やスケーラビリティのメリットがありますが、既存のインフラ環境や特定の要件により、オンプレミス環境の維持が適している場合もあります。移行の際には自社の運用方針やコスト、セキュリティ要件を考慮し、最適な移行先を選択することが大切です。
弊社では、既存のVMware環境を整理して、コスト、移行リスクなどの観点から最適な移行先をご提案する「VMwareまるっと移行サービス」をご提案しています。クラウド/オンプレミスのほかHyper-Vなど幅広くご相談ください。
ここでは、移行先として人気の高いクラウドサービスを3つ紹介します。
AWS
AWSは、VMwareからの移行をサポートするために、柔軟な選択肢を提供しています。特に、多くの企業が移行先として選ぶのが「Amazon EC2」です。Amazon EC2は、必要に応じてスペックを柔軟に増減できるため、コストを最適化しながら運用可能です。
これを支援するために、AWSは2つの重要なサービスを用意しています。1つは「AWS Application Migration Service(MGN)」で、VMware環境からの移行プロセスを自動化し、スムーズな移行を実現します。もう1つの「AWS VMware Migration Accelerator(VMA)」では、移行を促進しながらコスト削減とリスク軽減をサポートします。
VMWareからAWSへの移行をご検討の場合は、以下の動画をご確認ください。


Azure
Azureは、「Nutanix Cloud Clusters on Azure」を活用することで、VMwareからの移行をスムーズに実現するサービスを提供しています。Nutanix Cloud Clusters on Azureは、オンプレミスのNutanix環境とAzure上のクラウド環境を統合し、ハイブリッドクラウドとして柔軟に運用することが可能です。
また、このサービスでは、ハイブリッドクラウド上のNutanix環境で「Copilot」を活用できるため、仮想マシンの管理や最適化をより効率的に行うことができます。企業は、オンプレミスとクラウドを統合した環境を維持しながら、リソースの最適化や運用負担の軽減を実現できます。さらに、Azureのネイティブサービスとの統合により、クラウド移行後のアプリケーションパフォーマンスの向上やコスト削減も可能です。
VMWareからAzureへの移行をご検討の場合は、以下のページもご確認ください。
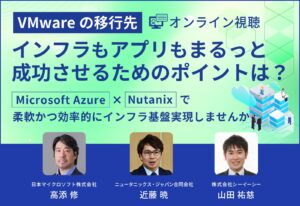
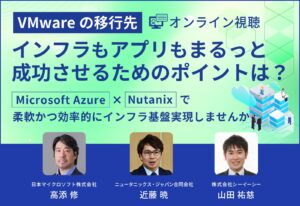
Red Hat
Red Hatは、「OpenShift Virtualization」を活用してVMwareからの移行を可能にするサービスです。仮想マシンとコンテナを統合的に管理することで、クラウドネイティブな環境への移行を加速できます。
Red Hatの特徴は、オープンソース技術に基づき、カスタマイズ性と柔軟性が高いことです。企業は既存の仮想マシンを無理なく移行しながら、同時に新しい運用モデルの導入を進めることもできるでしょう。この統合的なアプローチにより、運用コストの削減やシステムの最適化が期待できます。
VMWareからRed Hatへの移行をご検討の場合は、以下の動画をご確認ください。


移行における注意点
移行プロセスを成功させるためには、事前に現行のワークロードが移行先で正常に稼働するかを確認することが重要です。データの置き場所やネイティブサービスが要件を満たしているかについても、あらかじめ評価しておく必要があるでしょう。
また、移行に伴うダウンタイムやサポート体制についても慎重に検討する必要があります。各移行先の特性やサポート内容を比較し、適切な選択肢を見極めることが成功への鍵です。
VMwareからの移行をサポート!「VMware まるっと移行サービス」


VMwareから移行すべきなのか?VMwareからの移行先はどこにすべきなのか迷っていませんか?
それぞれの移行先の違いを把握し、自社にとって最適な選択ができるよう
移行検討から構築・運用までトータルでサポートご支援いたします。
VMwareから移行すべきなのか? VMwareからの移行先をどのように選べばいいのか?
一緒に最適解を見つけませんか
サービスについて詳しくはこちらから
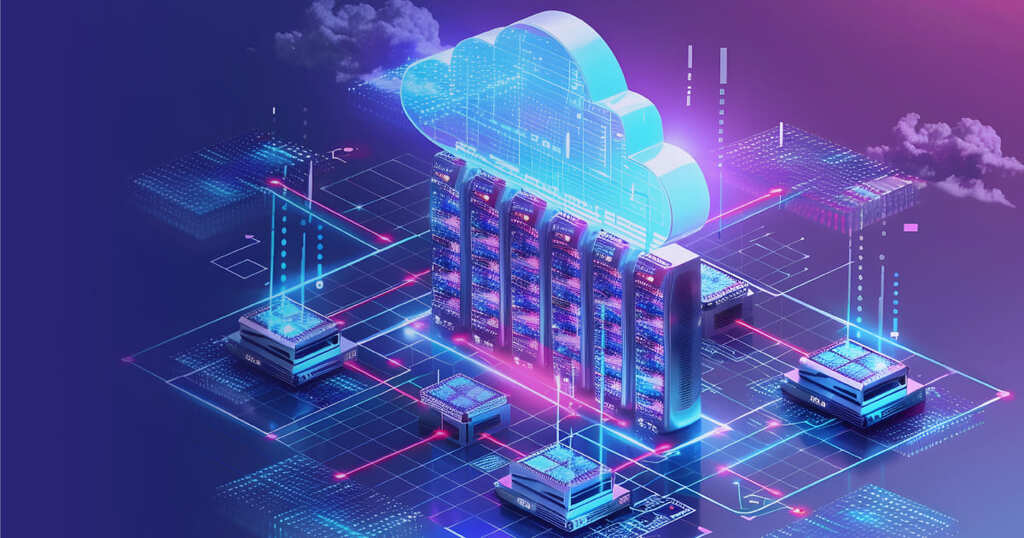
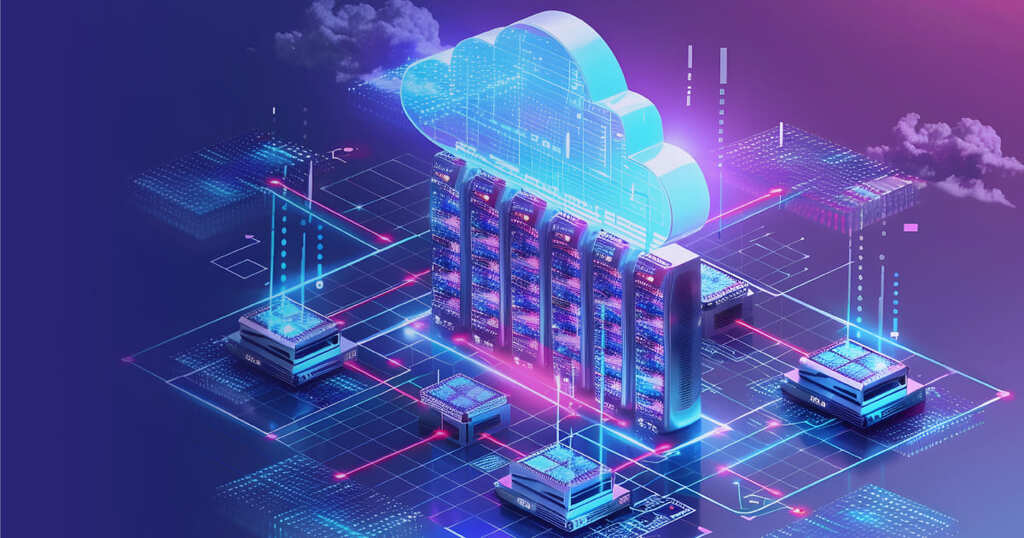
VMwareからの移行に関連するよくある質問
- エンタープライズ仮想化向けの最良の vmware 代替ソリューションは何ですか?
-
エンタープライズ仮想化向けの「最良」のVMware代替ソリューションは、企業の具体的な要件や既存のITインフラによって異なります。BroadcomによるVMware買収に伴うライセンス体系の変更 を受け、多くの企業が移行を検討しています。
主な代替ソリューションとしては、以下のものが挙げられます。
- AWS (Amazon Web Services):
対象システムをモダナイズしていきたい方 に特に推奨されます。クラウド環境への移行により、柔軟なスケーラビリティとコスト最適化が期待できます。 - Azure (Microsoft Azure):
特にWindows環境を利用しており、対象システムをモダナイズしていきたい方 に推奨されます。AWSと同様に高いスケーラビリティとクラウドのメリットを享受できます。 - Red Hat OpenShift:
ハイブリッド環境での運用を希望し、特にLinux環境でシステムをモダナイズしたい方 に適しています。コンテナ技術を活用した柔軟な環境構築が可能です。 - Nutanix:
ハイブリッド環境での運用を希望し、特に性能を求める方 に推奨されます。ハイパーコンバージドインフラ(HCI)として、高いパフォーマンスと運用効率を提供します。 - Hyper-V:
システムをそのまま利用し、運用を可能な限り変えたくない方 に適しています。オンプレミス環境での仮想化基盤として、既存のMicrosoft環境との親和性が高いです。
シーイーシーの「VMwareまるっと移行サービス」 では、お客様の環境やご状況に合わせて、これらの移行先を検討・提案し、移行・乗り換えをトータルでサポートします 。
最適な移行先を見つけるために、無料インフラ簡易アセスメントやアプリケーション・データベース移行無料診断サービスも提供しています。株式会社シーイーシー
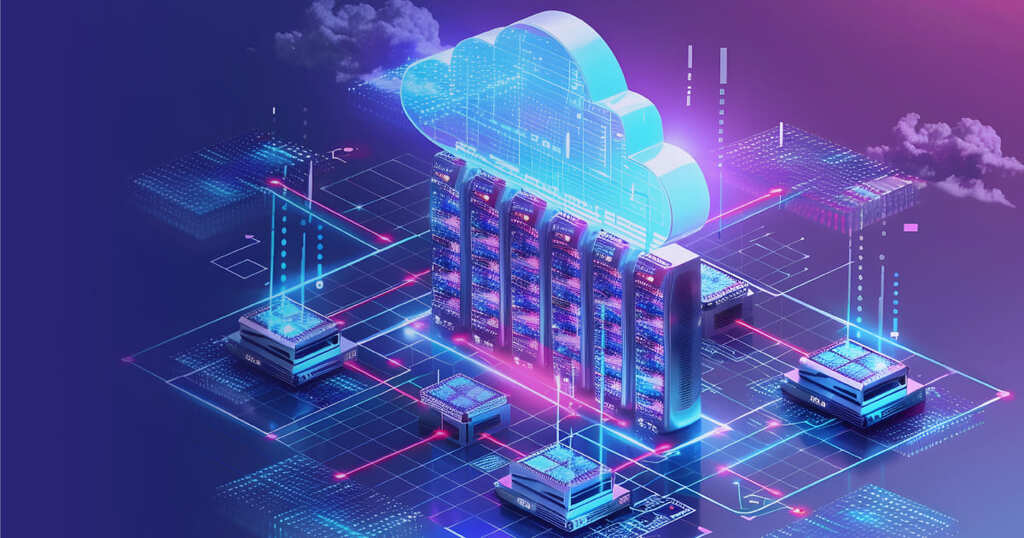 VMwareまるっと移行サービス|ICTソリューション総合サイト| 株式会社シーイーシー VMwareからの移行先でお悩みの方。シーイーシーでは、お客様の環境やご状況に合わせて、AWS、Azure、Red Hatなどの移行先を検討、提案、そしてVMwareからの移行・乗り換え…
VMwareまるっと移行サービス|ICTソリューション総合サイト| 株式会社シーイーシー VMwareからの移行先でお悩みの方。シーイーシーでは、お客様の環境やご状況に合わせて、AWS、Azure、Red Hatなどの移行先を検討、提案、そしてVMwareからの移行・乗り換え… - AWS (Amazon Web Services):
まとめ
VMwareのライセンス変更は、企業に多様な選択肢を提示しています。クラウド移行やオンプレミス維持といった幅広い可能性を検討し、自社に最適な移行先を見つけることが重要です。
また、移行プロセスに不安を抱える企業は、オンライン相談会や移行ガイドを活用することで、適切なサポートを受けられます。企業のIT環境の最適化に向けて、移行するべきか現状を維持するべきかを判断するためのサポートも行われています。企業の状況に応じた移行計画の策定が、今後の成功を左右することとなるでしょう。
VMWare移行については、以下の相談会もぜひご活用ください。専門家から課題の分析を受けられるだけでなく、自社に合った移行プランを気軽に質問できます。


VMware移行に関する資料のダウンロードはこちらから
関連サービス
既存のVMware環境(VM数、スペック、OSなど)を整理し、コスト、移行リスク、将来性の観点から最適な移行先をご提案します。また、インフラ層のみならずアプリケーション層およびDB(データベース)層の刷新、コンテナ化などのモダナイゼーションもお任せください。
「マイグレーションサービス」
特定の言語・製品・環境に縛られることなく、お客様のご希望に応じた組み合わせにて、ビジネス変化に強いICT資産に再生させるマイグレーションサービスです。
「データセンター ハウジングサービス」
お客様のシステムをデータセンター内にお預かりするサービスです。耐震性・耐火性に優れ、信頼性の高い空調/電源を安定的に供給できる環境をご用意します。
「セキュリティサービス」
お客様のシステムをデータセンター内にお預かりするサービスです。耐震性・耐火性に優れ、信頼性の高い空調/電源を安定的に供給できる環境をご用意します。