デジタルツインとは?主要技術やメリット、活用事例をわかりやすく解説

デジタルツインは、現実世界のあらゆるものを仮想空間に再現し、シミュレーションや予測に活用する最先端技術です。IoTやAI、5Gなどの複数の先進技術を組み合わせることで、製造業の生産性向上から都市計画、社会課題の解決まで幅広い分野で注目されています。本記事では、デジタルツインの基本的な概念から、シミュレーションやメタバースとの違い、技術要素、メリット、活用事例まで詳しく解説します。
デジタルツインとは

デジタルツインは2010年代後半から用いられ始めた比較的新しいIT用語であり、まだ一般にはそれほど浸透していません。ここでは、デジタルツインの定義や注目されている背景、関連技術との違いについてわかりやすく説明します。
デジタルツインの定義
デジタルツインとは、現実世界の物体やシステムをデジタル空間上で精密に再現する技術のことです。センサーやカメラなどで収集したリアルタイムデータをもとに、仮想空間上に「双子(ツイン)」となるモデルを作成します。現実の状態や動作をリアルタイムに反映・監視できるため、仮想空間でシミュレーションや最適化も可能です。現在では、製造業や都市開発、インフラ、医療などさまざまな分野で活用が進んでいます。
デジタルツインが注目されている背景
近年、Society5.0やDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されている中で、デジタルツインは業務効率化やコスト削減、新たな価値創出の手段として企業の関心を集めています。特にスマートファクトリーやスマートシティ分野での活用が拡大し、現実世界のデータをもとにした最適化やトラブル予測が可能になりました。今後、さらに多様な分野での導入が見込まれており、企業活動や社会インフラの根幹技術として重要性が高まることが予想されます。
デジタルツインとシミュレーションの違い
デジタルツインと従来のシミュレーションの大きな違いは、「リアルタイム性」と「現実世界へのフィードバック」です。シミュレーションは、あくまで仮想空間内での事前検証や予測を目的としています。一方、デジタルツインは現実世界のデータをリアルタイムで反映し、さらに仮想空間で得た分析結果を現実世界へ即座にフィードバックすることも可能です。
 未来図編集部
未来図編集部これにより、現実と仮想が常に連動し、高度な最適化や効率化が実現できます。
デジタルツインとメタバースの違い



デジタルツインとメタバースは、基本的な利用目的が異なります。
メタバースはアバターを用いた仮想体験や交流が主な目的であり、デジタルツインは現実世界の物体やシステム、プロセスなどをデジタルコピーし、現実課題の解決や最適化に活かすことが目的です。したがって、メタバースの仮想空間は、必ずしも現実世界を再現しているわけではありません。一方で、デジタルツインとメタバースを融合させれば、現実世界をデジタルコピーした仮想空間の中で、アバターを通じたバーチャルな体験を提供することもできます。
デジタルツインを支える主要な技術要素


デジタルツインは、IoTやAI、5G、AR/VR/MR/XR、CAEなど複数の技術を組み合わせることで実現しています。それぞれの技術が「データ収集」「分析」「可視化・体験」「シミュレーション」といった役割を担い、連携して機能します。
IoT:現実世界からのデータ収集
IoT(Internet of Things)は、センサーやカメラなどを活用し、現実の機器やプロセスの状態をインターネットを介して自動で取得する基盤技術です。



温度、振動、位置など現実世界の多様なデータをリアルタイムで収集し、仮想空間へ送信します。
デジタルツインにおいて、IoTは現実世界から仮想空間へつながる「入り口」となり、最新かつ正確な情報を反映する役割を担っています。デジタルツインの再現性をより高めるには、高精度なIoT機器に加え、安定したネットワーク環境やセキュリティ対策も重要です。
IoT関連の事例はこちら


IoT関連の相談会はこちら


AI:収集データの分析と予測
AIはデジタルツインの中核技術であり、IoTで集めた大量のデータを分析して異常検知や将来予測を行います。機械学習やディープラーニングの活用によってシミュレーションの精度が向上し、未来の挙動や故障の予測も可能です。こうした分析結果は運用の最適化や保守計画、制御命令に活用され、現実世界に反映されることで、実業務の高度化に寄与しています。



また、物流においては、在庫推移や需要動向などの予測にも応用でき、経営判断や資源配分の効率化に貢献します。
ビジネスでのAI活用についてはこちらから


生成AIについて詳しくはこちらから


5G:リアルタイムのデータ連携
5Gは大容量データの高速かつ低遅延な伝送を実現し、IoTから仮想空間への即時のデータ連携を可能にする通信技術です。多拠点間の情報共有や、移動体への安定した通信確保も実現します。5Gによってセンサー情報や解析結果を瞬時に反映することで、リアルタイム制御や遠隔対応が可能です。5GとIoT、AIの連携により、現実世界と仮想空間の間で遅延のない双方向データフローが構築できます。



ただし、導入状況は地域や業種によって異なるため、環境に応じた設計が求められます。
AR/VR/MR/XR:デジタル空間の可視化と体験
AR(拡張現実)は現実世界の映像に仮想情報を重ねる技術であり、VR(仮想現実)は仮想環境に没入する視覚表現技術です。さらにMR(複合現実)は、現実世界と仮想空間の情報を高度に融合し、双方向の操作や反応を可能にします。そして、AR/VR/MRなどの先端技術を包括的に指す言葉がXR(クロスリアリティ/エクステンデッドリアリティ)です。デジタルツインの分析結果や仮想モデルをAR/VR/MR/XRで可視化することで、直感的な理解や遠隔操作ができます。例えば、工場や都市の設備を3Dモデルで表示しながら遠隔操作やトレーニングを行うことが可能です。



現場作業者や管理者が仮想情報をリアルタイムで共有・操作できるため、業務精度や安全性の向上が期待できます。
CAE:仮想空間での高度なシミュレーションを実行
CAE(Computer Aided Engineering)は、コンピューター上で製品や構造物の強度・温度・振動などを精密にシミュレーションする技術です。



デジタルツインの仮想モデルにCAEを連携することで、現実では検証が困難なシナリオでも高精度に解析できます。
具体的な応用例は、構造物の最適設計や故障リスクの予測、事前の耐久評価などです。CAEの結果は、AIの学習や現実世界への制御命令にフィードバックされ、高度な最適化プロセスの構築に役立てられています。
デジタルツイン導入がもたらす多角的なメリット


デジタルツインは、製造業やインフラ分野で効率化・品質改善・コスト抑制・保全強化など多様な効果をもたらします。ここでは、デジタルツインの導入で得られるメリットを解説します。
生産性の向上と業務効率化
仮想空間上で製造工程や生産ラインを再現することで、試作や工程変更を素早くでき、リードタイムの短縮をシミュレーションできます。ビッグデータとAI分析を活用すれば、最適な設備構成や人員配置、工程順序を検討できるため、全体の業務効率向上が図れます。



データにもとづく運用改善が進み、余剰コストや停滞時間も減少して生産性や業務効率の向上が期待できます。
品質向上とリスクの低減
デジタルツイン上で詳細な品質シミュレーションを繰り返すことで、欠陥発生の兆候を早期に検出・分析できます。潜在的な問題を可視化することで原因を突き止めやすくなり、事前対策も容易です。結果として不良品率が低下し、品質のばらつきを抑えられます。複雑なシステム・工程においてもリスク把握の精度を向上させ、重大インシデントの発生リスクを低減し、予防につなげることが可能です。
設備保全・予知保全の実現
センサーから収集した稼働データをAIで解析し、異常発生や劣化傾向の予測を高められます。故障リスクを早期に察知し、計画的な保守作業も可能です。



ダウンタイムの大幅削減に貢献し、メンテナンスコストの低減や安全性の確保、稼働率の向上が期待できます。
開発期間の短縮とコスト削減
仮想環境での設計や性能検証を繰り返すことで、実物試作を減らし、開発期間の短縮を可能にします。開発フェーズの一部を効率化することで、設計や試作にかかるコストも大幅に削減できます。SCMや部品調達の効率化も進み、プロセス全体の省エネ化・省コスト化につながります。
- SCM(サプライチェーンマネジメント):原材料調達、製造、物流、販売といった製品流通の全プロセスを一元的に管理すること。
遠隔地からの作業支援と技術伝承
デジタルツインとXRやリモート接続を組み合わせることで、遠隔地の熟練者が現場作業を指導・監督できます。また、作業手順やノウハウをデジタル空間に記録することで、長期的な技能継承の仕組みも整えられます。



地理的な制約を受けることなしに人材教育・人材育成が進められる点も大きなメリットです。
アフターサービスの充実と顧客満足度向上
デジタルツインによって出荷後の製品を仮想モデルで継続的に監視し、使用状況や劣化状態などをリアルタイムで把握することが可能です。部品の消耗具合や故障の兆候に応じて、最適なタイミングでメンテナンスやサポートを提供できます。



これによりアフターサービスの質が向上し、顧客満足度やブランド価値も高められます。
社会課題解決への貢献
気象災害やインフラ劣化などの公共課題に対して、デジタル防災訓練や都市モニタリングといった形でデジタルツインの活用が広がっています。農業分野やエネルギー分野でも、仮想環境を活用した効率化や持続可能性の向上を目指した施策設計が可能です。



また、地球規模の課題に対して、コストやリスクを抑えながら実証実験や対策検討を行えるデジタルツイン構築事業も進められています。
デジタルツインの活用事例


製造業、都市、医療、交通、防災など多様な分野で現実世界に即したモデルに基づく最適化・予測・理解が進んでいます。ここでは各分野の代表的な事例を紹介し、その効果を紹介します。
製造業:工場の24時間操業やロス低減を実現
センサーとAIを組み合わせたデジタルツインにより、設備の稼働状況や生産プロセスのリアルタイム監視と、故障の予兆の早期検知が可能です。このようなデジタルツインの活用は、部品交換のタイミングの最適化、無駄な作業の削減、生産計画の遵守に役立っています。さらに、工場内の設備停止の最小化は、稼働率の向上やラインのロス削減に有効です。



近年、多くのメーカーがデジタルツインを活用したスマートファクトリー化を進め、生産性と信頼性の両立を実現しています。
都市計画・スマートシティ:国土交通省「Project PLATEAU」や東京・八王子市の取り組み
国土交通省が推進する「Project PLATEAU」では、3D都市モデルが共通プラットフォームとして整備され、都市開発や防災、交通計画など幅広い分野で活用されています。すでに全国約250都市で3Dモデルが完成し、市民・企業・自治体でのデータ共有や利用が進んでいます。八王子市ではXRを活用したワークショップが開催され、住民が都市計画案を直感的に理解しやすい仕組みも導入されました。



災害時の避難経路シミュレーションや人流解析にも役立っており、住民参加型の都市開発や政策決定に貢献しています。
医療・ヘルスケア:患者個々の状態を再現した手術リハーサルに活用
患者の臓器や疾患状態を3Dモデルで再現し、手術の手順やリスクを事前にシミュレーションすることで、安全性が大きく向上しています。患者ごとに最適化した治療計画を立てやすくなり、術後合併症のリスク低減や患者の身体的負担軽減にも役立っています。今後は個々のバイタルデータとの連携により、医療現場において「パーソナルデジタルツイン」の活用がさらに拡大していく見通しです。
交通・モビリティ:自動車の走行状態識別や都市交通シミュレーションに応用
自動車に搭載されたセンサー情報を活用して仮想モデルを作成し、走行状態や異常挙動をリアルタイムで検知・分析できる技術が開発されています。都市レベルで交通流や信号制御、渋滞予測を仮想空間でシミュレーションできるため、交通マネジメント支援に活用可能です。



デジタルツインを用いることで、都市全体の移動効率が向上し、排ガス量の抑制や物流の最適化につながります。
災害対策・防災:「防災版デジタルツイン」による未来予測
建設業やインフラ管理企業では、河川や堤防、橋梁の3Dモデルに水位・流量・地形変化のデータを重ねることで、洪水をはじめとする災害リスクの予測に活用しています。多様なシナリオで避難経路や被害範囲を可視化できるため、実効的な防災計画策定にも有用です。施工段階から完成後の防災管理まで一貫してデジタルツインを活用し、地域住民に情報提供を行っている企業もあります。
その他の業界・分野
デジタルツインは多くの業界・分野で活用が進められています。小売業界では、店内のレイアウトやバックヤードの動線をシミュレーションして、売上の向上や店舗運営の効率化に活かせます。航空業界では、エンジンの摩耗や振動データをもとにしたメンテナンス予測に活用することで、運航停止リスクの抑制が可能です。



建設現場では、施工進捗や資材配置を仮想空間で可視化し、安全管理や作業効率向上に役立てる取り組みが拡大しています。
デジタルツインの課題と将来性


デジタルツインには導入コストやセキュリティ確保などの課題があります。その一方で、市場拡大や技術進化といった将来への期待も高まっています。
課題:高額な導入コストとデータセキュリティの確保
デジタルツインを導入するには、センサーの設置や3Dモデルの構築、リアルタイムデータ処理体制の整備など、多額の初期投資が求められます。さらに、大規模システムの運用や保守にも継続的なコストが発生するため、ROI(投資対効果)の確保が重要なポイントです。セキュリティ面では、IoT機器経由の不正アクセスやデータ漏えいといったリスクが伴い、暗号化やアクセス制御などの対策が不可欠です。加えて、既存システムとの連携や専門人材の不足も課題となり、段階的なPoC(概念実証)や専門人材の育成が望まれます。
将来性:市場規模の拡大と技術進化の加速
デジタルツインの日本市場は2024年時点で約15億米ドルと推計され、2025年から年平均成長率約28%で拡大し、2033年には186億米ドルを超える見込みです。世界市場においては、2025年の約2450億米ドルから2032年には約2.6兆米ドルまで急成長するという予測もあります。IoTやAI、5G、エッジ技術の進化とともに、デジタルツインのインフラ化(IoDT=Internet of Digital Twins)が進み、精度や応用範囲、安全性が大きく向上することが期待されています。今後はさまざまな産業や社会インフラで導入が進み、DXやSociety5.0の本格化を支えるコア技術として定着していくでしょう。
デジタルツインは次世代のビジネスを切り開く革新的技術
デジタルツインは現実世界と連動する仮想モデルを用い、さまざまな産業に多角的な価値をもたらしています。



すでに多様な分野で活用され、実証効果も明らかになりつつあります。
導入コストやセキュリティ面に課題はあるものの、市場規模は急拡大しており、今後の社会基盤となる可能性が高いです。DXやSociety5.0の推進にもつながり、企業の競争力や社会的価値を向上させる革新的技術といえます。
関連するソリューションの詳細はこちら
その他のコラム記事はこちらから
-



SSOだけが解ではない!医療現場に求められる“現実的な”認証強化策
-



GPUサーバーとは?導入メリットや活用シーン、選定ポイントを解説
-



子育て支援アプリat Clapsの社会貢献活動を支えるAWSの活用事例
-



デジタルツインとは?主要技術やメリット、活用事例をわかりやすく解説
-



エージェント型AIとは?仕組みやメリット、活用事例、課題を解説
-


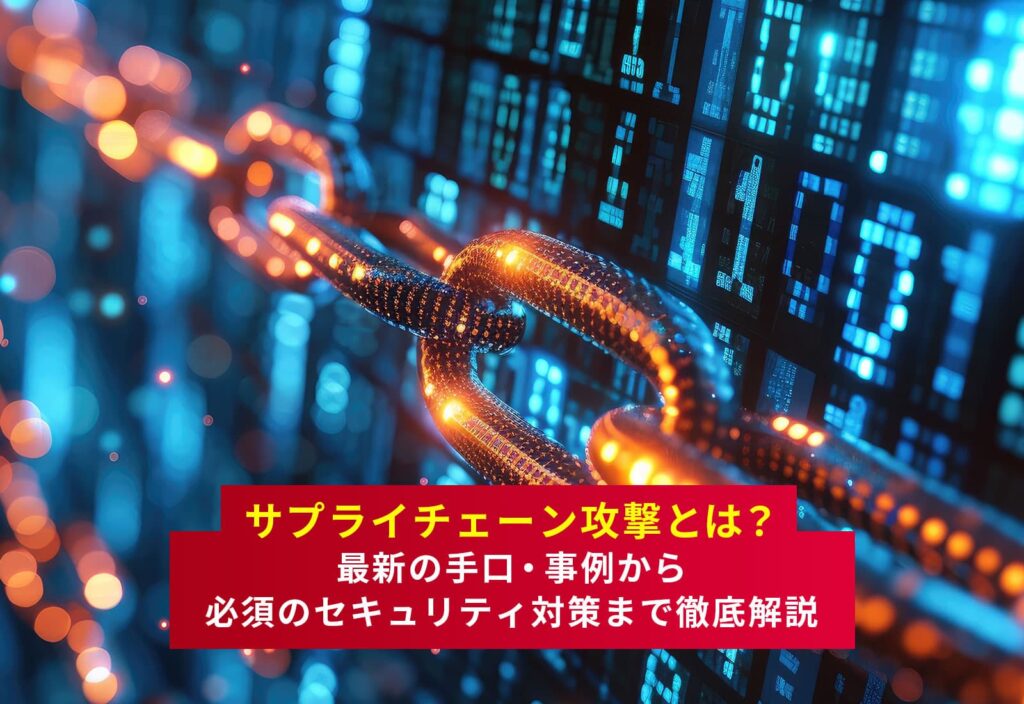
サプライチェーン攻撃とは?最新の手口・事例から必須のセキュリティ対策まで徹底解説
-



Intuneとは?導入のメリットとデメリット
-



AI活用でビジネスを加速!選び方から導入支援まで徹底解説
-



情シス革命!Windows Autopilotで実現する快適なPCキッティングの未来

